エクセル学習総合サイト |
||||
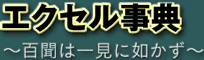 |
||||
|
スポンサード リンク
スポンサード リンク
|
|||
「配列数式の計算ルール:セル範囲(一般論)」で説明した通り、n行m列の配列を得るためには、その計算元となる配列も、n行m列でなければならないことを、勉強しました。 基本原則は変わりませんが、例外的な使い方がありますので、ここに説明します。 |
|||
「1行m列」と「n行m列」の計算 |
|||
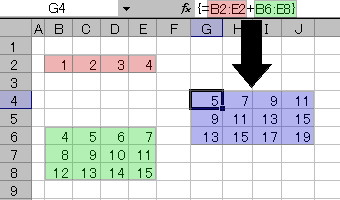 |
1 「1行4列」のセル範囲(赤部分)と「3行4列」(緑部分)の計算結果は「3行4列」(青部分)になる。 |
||
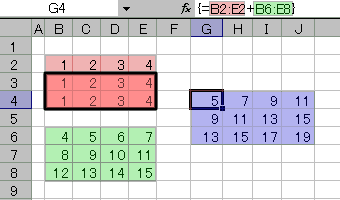 |
2 エクセルは、計算結果が「3行4列」になるように、左図の黒枠で囲まれた赤部分を、暗黙の内に作り、一般論で記述した計算方法で計算をする。 |
||
「n行1列」と「n行m列」の計算 |
|||
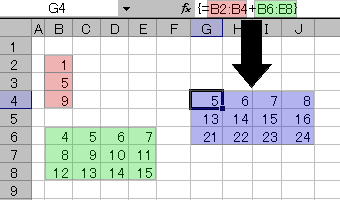 |
1 「3行1列」のセル範囲(赤部分)と「3行4列」(緑部分)の計算結果は「3行4列」(青部分)になる。 |
||
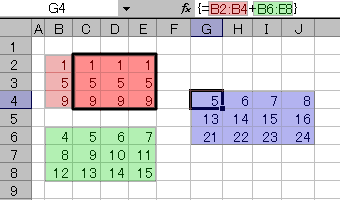 |
2 エクセルは、計算結果が「3行4列」になるように、左図の黒枠で囲まれた赤部分を、暗黙の内に作り、一般論で記述した計算方法で計算をする。 |
||
「n行1列」と「1行m列」の計算 |
|||
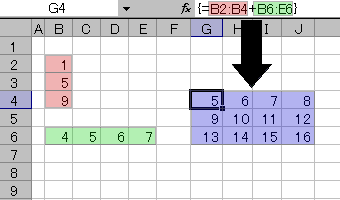 |
1 「3行1列」のセル範囲(赤部分)と「1行4列」(緑部分)の計算結果は「3行4列」(青部分)になる。 |
||
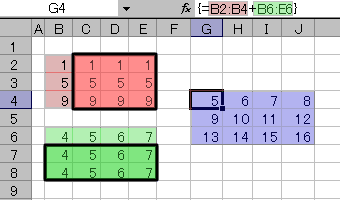 |
2 エクセルは、計算結果が「3行4列」になるように、左図の黒枠で囲まれた赤部分と緑部分を、暗黙の内に作り、一般論で記述した計算方法で計算をする。 |
||
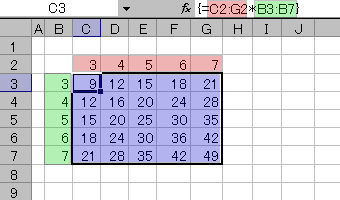 |
3 これを応用すれば、九九の表などを簡単に作成できる。 |
||
|
スポンサード リンク
|
||
| ▲このページの上へ | ||
| <- 前へ | 目次 | 次へ -> |